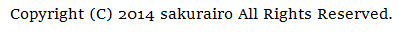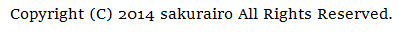4 彼の過去
数日後。
私たちは定時で仕事を終わらせ、それから高倉さんの車でお店へ向かった。
そのお店はうちの会社が設計した和食創作料理のお店で、建物もお洒落だし料理も美味しいと評判だった。
お店の中へ進み、個室へ案内された。
この雰囲気が余計に緊張させる。
勧められたまま座布団に座り、そのまま動けなかった。
「コート、脱がないの? 寒い?」
「あ…」
慌ててコートを脱ぐと、高倉さんは「貸して」と壁のハンガーに掛けてくれた。
「何がいい?」
「お任せします」
「嫌いなものは?」
「特にありません」
正座をして、手はひざに置いたままの私に
「この店来たことあった?」
と高倉さんは尋ねてきた。
きっと気を遣ってくれたんだろう。
いつもなら逆なのに…。
結局その質問にも「いいえ」だけしか答えられなかった。
しばらくして来たお料理も箸を持ったまま、口にすることができなかった。
「どうした? 具合悪い?」
「いいえ」
高倉さんの“大事な話”が何なのか気になって、食欲も出ない。
「あの、大事な話って何ですか?」
「ああ…。実は…」
やっぱり聞きたくない!!
だったら自分の口から切り出した方がマシだ。
「そう言えばこの間、佑莉が働いているお店に行ったんですよね?」
私は高倉さんの言葉を遮ってしまった。
「佑莉ちゃんから聞いた?」
佑莉“ちゃん”か…。
いいな…。
私と違って佑莉は可愛いから。
きっと高倉さんは佑莉のこと…。
「あの子は本当にいい子ですよ。
下に弟と妹がいるから、両親に負担をかけないようにって進学を諦めて、高校を卒業して就職したんです。
大学を卒業してもう一年専門学校に行くことになった私のことも一言も文句言わずに応援してくれた。
弟と妹の受験が重なったときも部屋がなくて、本当は一番年上の私が家を出ないといけないのに
佑莉は“お姉ちゃんは社会人1年目だから”と言って寂しがりやのくせに無理して一人で暮らし始めたんですよ。
他の事でもそう。自分よりも他の兄弟のことを優先してしまうんです。
だから高倉さん、どうか佑莉を幸せにしてあげてください」
今まで佑莉がしてくれたように、今度は私が佑莉の気持ちを一番に考えてあげたいと思った。
すると
「君と佑莉ちゃんとお母さんはそっくりだね。早とちりで…」
急に高倉さんは笑い出した。
こんなに笑っているところ初めて見た。
高倉さんは立ち上がって、向かいに座っていた私の横に腰を下ろし
いつのまにか流していた涙をハンカチで拭いてくれた。
「佑莉ちゃんも、桐原さんも、本当にいい子だよ。
あ…、いい子っていう言い方は失礼かな。素敵な女性だと思う。
きっとご両親が4人に分け隔てなく愛情を注いで育てたからじゃないかな。
佑莉ちゃんも桐原さんのことをすごく尊敬してるって言ってたよ」
高倉さんがそこまで話すと「失礼します」と襖が開けられ、横に並んだ私たちを見たお店の人は
「申し訳ありません」と一旦引き下がろうとした。
「すみません。気にしないでください。今から食べますので…」
と高倉さんは自分の席に戻った。
お店の人がテーブルにメイン料理を並べ部屋から出て行くと
「とにかく佑莉ちゃんとは何もないから。あの店に入ったら偶然働いていて驚いたよ。
さ、とりあえず先にご飯食べよう」
私はその言葉を聞いて、なんとか少しずつ食べることができた。
評判通り、とても美味しい料理だった。
お店を出て車に乗ると
「さっきの話しの続きがあるんだけど、時間いいかな」
「…はい」
車は大通りをしばらく走り、住宅街を抜け、暗い上り坂を抜けると
フロントガラスいっぱいに夜景が広がった。
高倉さんは私が思っていた以上に、大人で、デートもいっぱいしてきて
こういういう場所にさりげなく連れてきちゃう程、女の人に慣れているのかなと思った。
「実はね、さっきの話には続きがあって。
僕にも妹がいて、佑莉ちゃんと同じ年だったんだ…。もし生きていれば…」
妹さんが生きていれば…?
「それで年齢を聞いて、つい妹と重ねてしまった。
佑莉ちゃんと話してると、妹と話しているみたいで妹が目の前にいるんじゃないかって錯覚しそうだった。
妹は僕が今の会社に入社した年に亡くなったんだよ。19歳になってすぐだった。
子供の頃から体が弱くて、入退院ばかりしていた。
両親はそのことでいつも喧嘩して、父親はいつからか家に帰って来なくなった。
僕は高校生の時に、父親が帰って来たくなるような家を造りたいと思った。
妹が車椅子生活になっても暮らしやすく、母親は妹の看病をしながら家事を楽にできるようにって
そういう間取りばかり考えていた。
しかし結局は、建築家になることはできたけれど、夢は叶えられなかった」
私はどう相槌をしたらいいか判らなくて、ただ黙って話を聞いていた。
「妹は最期『お兄ちゃん、私はまだ死にたくない…』って言いながら永遠の眠りについた。
そんな妹のことが忘れられなくて、ずっと自分だけ幸せにはなれない。
人生を楽しんだり、誰かに干渉したり、誰かを好きになることもしないように生きてきた。
その分、他人(ひと)の幸せを願いたいと、元々“幸せな家”を作ることが夢だったから
建築家という仕事は、こんな自分にとってはちょうどよかった。
だけど君と仕事をして、君の家族と会って、一緒にご飯を食べて……
僕は幸せになりたいと思ってしまった」
高倉さんはハンドルにもたれ、顔を伏せた。
「どうして…幸せになりたいと思っちゃいけないんですか?」
触れようと手を伸ばしたけれど、やっぱり触れることができなくて、伸ばした手を引っ込めた。
「私がもし高倉さんの妹さんの立場だったら、自分の分も幸せになってほしいと思います。
高倉さんは、亡くなった妹さんのためにも幸せにならないといけないんじゃないかな…。
少なくとも私は、好きな人には幸せになってもらいたい」
その言葉に、高倉さんはゆっくりと顔を上げた。
「高倉さん、私と一緒に幸せになってくれませんか?」
まるでプロポーズのような告白をすると、どちらからともなく静かにキスを交わした。
←back next→
2007-02-08
|| top ||
novel ||
blog ||
link ||
mail ||
index ||