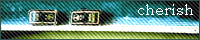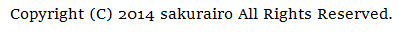52、泣顔
夕焼けでオレンジ色に染まり始めていた部屋は、いつの間にか真っ暗になっていた。
若葉はソファで眠ってしまったらしく、寝心地の良さに寝室に移動していたことを知る。 けれど一緒に寝ていたはずのリョウが隣にいない。寝室のドアを開けるとキッチンの明かりが目に入った。眩しくて目を細める。
「先生?」
声をかけると、リョウは木ベラを手に持ち、キッチンから若葉の方を見た。
「あ。起きた?」
「うん……」
若葉は目をこすりながらキッチンに入ると、リョウがチャーハンを作ってくれていることがわかる。
「起こしてくれれば、私が作ったのに」
「あまりにも気持ちよさそうに眠っているから、起こすのは可哀想だと思ってさ」
炒めながらリョウは言った。以前は自分で料理をすることなどほとんどなかったが、 若葉と外食するも互いに気を遣うし、だからと言って市販の弁当や惣菜などは一人の時だけで充分だ。
若葉は彼が一生懸命料理を作ってくれる姿を見ていたら、愛しさが再びこみ上げてきて、たまらず彼の背後から腰に抱きついた。
「コラ、危ないって」
リョウはコンロのスイッチを切り、若葉の方を振り返り抱き締めた。
「先生、私より先に起きちゃダメだよ。どっかに行っちゃったかと思うでしょ」
「どっか行くって、自分の部屋なんだから……」
頭では理解していても、些細なことで不安になってしまう。
「よしよし。ほらご飯出来たよ。不味くはないと思うけど」
「うん」
若葉はパッと手を離して、皿とスプーンの準備をしようとすると「ゲンキンなやつ」と笑われてしまった。
「美味しそう。いただきます!」
若葉はチャーハンを一口食べて「美味しいよ」と二口目を運ぶ。
リョウはそんな彼女の姿をじっと見つめる。
「ん?」
「若葉は美味しそうに食べるな。俺、その顔が一番好きかも」
「食べている時の顔が好きって言うのは、食いしん坊みたいで、ちょっと恥ずかしいよ」
「そっか?」
間近で見られ、そんなこと言われると意識して食べられなくなってしまう。
「美味しそうに食べている時の顔も、笑っている顔も、怒っている顔も、それから泣き顔も、全部好きなんだよ」
リョウは真っ直ぐな瞳で言った。
「だから自分の感情を抑えないで。最近、若葉は泣くのを我慢しているだろ? 一週間のうち、ほとんど毎日若葉の顔を見ているんだよ。それくらい判るんだ」
「うん」
若葉は自他ともに認めるほどの泣き虫だ。リョウを好きになるきっかけの時も、 元カレに振られて泣いていた。リョウに好きだと言ってもらえた時も泣いた。 修学旅行の時は一生分泣いたなと思うくらい泣いた。何かあるたびに泣いていたら、 そのうち重い自分は振られるかもしれない。リョウにだけは嫌われたくない。
だから若葉は十八歳の誕生日に、もうリョウの前で泣いて困らせないと決心をしたのだ。
そう思っていたのに、リョウには気付かれていた。
リョウのことが大好きでたまらないのに、言葉の他に表わすこと術がわからなくてもどかしい。
「先生、泣いてもいい?」
「いいけど、食べてからにしよう……ってもう泣いているし」
リョウは苦笑いをしながら、それでも若葉のことが可愛くて、そばによりティッシュで涙と鼻水を拭いた。
若葉はこうしてくれることが久しぶりでまた泣けてくる。
「おいおい。泣き止め」
魔法をかけるようにリョウの大きな両手は若葉の頬を包み込み、彼女の瞳にキスをした。
←back next→
「cherish」目次へ戻る
・・・・・・・・・・
2006-05-28
2012-07-05 大幅修正
2013-09-20 改稿